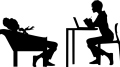よく笑う人の5つの心理とは?
ポジティブ思考
ここからは、よく笑う人の心理について詳しく見ていきます。
生きることを楽しんでいる人は、とにかくよく笑います。悲しい顔を見せません。あらゆる出来事をポジティブに解釈することができるからです。
いつもポジティブな気持ちでいるための秘訣は、自分の意志で生きることにあります。
自分自身で下した決断に従って生きているため、何があっても他人のせいにしません。楽しいことも苦しいことも、素直に受け入れることができるのです。
調子のいいときも悪いときも、ありのままの自分を素直に認めることができます。そのため、どんなときも前向きな気持ちでいられるのです。
たとえば、2人の野球部員を例に考えてみましょう。ひとりは、自分の意志で野球部に入りました。もうひとりは、親に言われてしぶしぶ野球部に入りました。
親に言われて入部した部員は、つらいことがあると「辞めたい」と思ってしまいます。親のせいで辛い目に合っていると考えるからです。
そのため、練習に義務感しか感じません。つらい練習に耐えなければという気持ちしかわかないので、滅多に笑うことがなくなってしまいます。
一方、自分の意志で入部した部員は、つらいこともあると最初から覚悟しています。つらい目に合っているのも、自分自身の選択なのです。
自分自身の選択である以上、簡単に逃げようとは思いません。むしろ、つらいことを乗り越えた先にある成長を見据えています。
そのため自分の意志で入部した部員は、つらい練習の中でも笑顔を忘れません。どんな状況にあっても、前向きにポジティブな気持ちを忘れずによく笑うのです。
周りの人に対して配慮している
いつもポジティブな気持ちになれるわけではなくても、それでもよく笑うことのできる人がいます。内心は泣きたいような気持ちなのに、顔ではいつも笑っているような人です。
悲しい気持ちとは裏腹に笑顔を見せる人は、周囲の人の気持ちを第一に考えています。周囲の人を暗い気持ちにさせないために、必死で笑っているのです。
たとえば、長年飼っていたペットを亡くしてしまった人を例に考えてみましょう。自分の分身のように大切な存在だったペットを失い、深い悲しみに暮れています。
それでも、悲しみを表に出すことはしません。周囲の人たちを自分の悲しみに巻き込みたくないからです。友達に対しても、職場の同僚に対しても、いつものように笑顔で接するのです。
また、ペットを失った悲しみにもかかわらず笑顔でいるのは、自分の気持ちを奮い立たせるためでもあります。
悲しい顔でいるままだと、悲しみは深まるばかりです。逆に表情だけでも笑顔を作るようにすると、少しずつ気持ちも明るくなっていくものです。
無理をしてでも笑顔を作ることで、自分自身がペットを失った悲しみから抜け出そうともしているのです。
よく笑う人は、第三者からすると幸せそうに見えます。しかし、内面には深い悲しみを抱えていることがあります。笑うことで、内なる悲しみと戦っているのです。
みんなと仲良くなりたい
笑顔には、相手の警戒心を解く効能があります。笑うことには「仲良くなりたい」という友好的なメッセージが含まれているからです。
したがって「周りの人たちと仲良くなりたい」と思っている人は、よく笑います。笑顔を見せることで、「仲良くなりたい」という気持ちを伝えようとしているのです。
たとえば、小学生や中学生の頃を思い出してみてください。クラス替えがあると、新しいクラスでも友達ができるのか、不安になったのではないでしょうか。
クラス替え当日は緊張のあまり、周りの生徒にうまく話しかけられない人もいます。しかし「みんなと仲良くなりたい」という思いが強い人は、初対面の相手に対しても笑顔で接します。
笑顔を浮かべている人は、周りの人たちの警戒心を解くことができます。新しいクラスの中でも、「話しかけやすい人」というイメージを持ってもらえます。
話しかけやすい人の周りには、新しいクラスメイトが次々と集まってきます。人が集まってくると、笑顔を見せる機会も増えていきます。自然と「よく笑う」ことになるのです。
本心を隠そうとしている
一方、笑顔の友好的な意味合いを逆に利用して、本心を隠そうとする人もいます。本心では敵対的な気持ちを持っているにもかかわらず、笑顔という仮面で本心を隠そうとするのです。
たとえば、ビジネスの取引の場面では「仮面」としての笑顔があふれています。
シビアな取引の当事者間には、一歩も引けない利害関係があります。本心では、相手を出し抜くことを考えています。とはいえ、本心がバレるのも具合が良くありません。
そこで、本心を隠すために「仮面」としての笑顔が使われます。表向きは友好的な雰囲気を演出することで、水面下で繰り広げられる争いを隠そうとするのです。
同じようなことは、外交の場面でも行われます。緊張関係にある国家間で首脳会談が行われる場合、メディアの前では友好的なムードを醸し出します。その裏でし烈な交渉が行われるのです。
ビジネスや政治の場面では、「仮面」としての笑顔は便利な道具としてよく使われます。しかし、個人的な生活において「仮面」としての笑顔が多用されると精神衛生上よくありません。
たとえば、友人関係の中で本心を隠すための笑顔が使われると、友情に疑いが向けられてしまいます。最悪、誰のことも信用できなくなります。
本心を隠すための笑顔に日常的に囲まれると、人の精神は病んでしまうのです。
事なかれ主義
重要な決断を避けたくて「笑顔でごまかす」という場合もあります。意見の対立よりも現状維持を選びたい一心から、あいまいな笑顔でその場をしのごうとするのです。
たとえば、マンションの管理組合を例に考えてみましょう。台風の被害で壊れた共有部分の修理について、住民の間で意見が割れているとします。
理事会で会議を開いても、なかなか意見がまとまりません。議論は堂々巡りになってしまいます。しかし、肝心の理事長は特に意見を言うこともなく、ただ笑ってばかりいます。
この場合、笑うことが問題の解決を遠ざけてしまいます。本当に問題を解決するには、多少雰囲気が悪くなっても、住民同士の意見を戦わせる必要があります。
にもかかわらず、対立を避けたいがために笑ってばかりいるようでは、建設的な議論がまったく進みません。理事長の笑顔は、事なかれ主義の表れでしかないのです。
人間関係を進めていくうえでは、時に衝突が必要になることもあります。必要な衝突まで避けようとして笑うことは、問題の先延ばしにしかなりません。